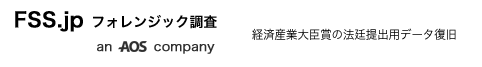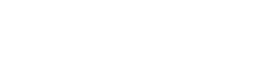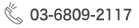5月31日 昨日は経団連が発表した「グリーントランスフォーメーション(GX)に向けて<概要>」についてから、昨今話題となる「グリーントランスフォーメーション」(GX)とは何かを探って来た。本日はその第3回目となる。2050年CNを実現するために必要な方策(GX政策パッケージ)には産業構造の変化への対応も想定されている。政府の「成長戦略実行計画」では、グリーン成長に向けた新たな投資の柱として、CNに伴う産業構造転換・産業構造転換に伴う失業なき労働移動(公正な移行)の支援について、2050年CNの影響を受ける産業の労働者は約250万人(エネルギー多消費産業および化石燃料に携わるエネルギー産業の常時従業者数の合計)とされ、これらの層に対し求められる施策としては、円滑な事業転換等に向けた支援(CNに伴う円滑な事業転換等を促す時限立法、CNへの国際競争力の観点から、国内の企業・組織再編を促す環境整備等)と、円滑な労働移動の推進(リカレント教育やリスキリングの充実・強化、企業・グループ内における労働移動、社会全体での労働移動)とされる。2つの施策は企業や団体などの事業向け支援策と、内部で労働に従事する人材向けの支援と見られる。また、現在政府が推進する意図への投資の抜本的強化のための4000億円施策パッケージに、GXの担い手となる労働力の量と質を確保するための様々な措置を盛り込むべきとしている。資料中の参考(30頁)GXを通じた業態転換・労働移動のイメージとしては、既存のCO2多排出事業は転換を迫られる一方、CNに大きな役割を果たす新事業が生まれ雇用が創出される見通しが示され、同時にCNへの挑戦を経済成長に繋げるため、新事業への転換・労働移動(社内・社外)を円滑に進める必要があるとしている。また「カーボンプライシング」については、炭素排出に価格を付け、経済的インセンティブにより、民間活力を活かしながら排出主体の削減を促す政策手法と定義、抜本的なイノベーションに繋がる制度設計を行い、産業競争力への影響を検証した上で、適切なタイミングで導入できれば、CNを実現する手段となり得ると評価、カーボンプライシングの類型は多様であるが、これらの中で成長に資する仕組みを導入すべきとしている。例としては、炭素税、キャップ&トレード型の排出量取引制度、エネルギー関係諸税、FIT賦課金、クレジット取引、インターナショナル・カーボンプライシング、自主的な取組等が挙がる。カーボンプライシングの類型選択にあたっては、排出削減効果やマクロ経済・産業競争力への影響(国際競争に晒され、かつ削減手段のない産業への時間軸を踏まえた配慮)、国民負担の在り方(負担の受容性、価格転嫁のあり方、公平性)、社会全体として効率的な削減の実現、我が国の他の制度・仕組みとの関係(補完関係や相乗効果があるか、スクラップ&ビルドが必要か)、国際的整合性を考慮すべきとしている。続く、考慮事項を踏まえたカーボンプライシングにおいて(経団連は)現状のCN行動計画とGXリーグは「経団連 カーボンニュートラル行動計画」(各業界のCO2削減に向けた主体的な取組み)は、前述した考慮事項を概ね満たすものとし、これまで着実な取り組みが進み、国の地球温暖化対策計画の柱にも位置付けられており、政府は「GXリーグ」(クレジット市場を通じた企業による自主的な排出量取引等)に関する基本構想を提案している。政府が掲げる目標達成に向け、かような主体的取り組みや、省エネ法等の規制とともに、カーボンプライシングを含め様々なポリシーミックスのあり方を絶え間なく検討して行く必要があるとしている。脱炭素税については排出量を固定できない上、排出削減効果は限定的であり、気候の厳しい地域をはじめとする国民生活の負担になるのみならず、国際的に既に高いエネルギー・コストを負担している産業の国際競争力を損なう恐れが高いと評価している。キャップ&トレード型の排出量取引制度*については、削減の確実性を担保しつつ、産業競争力への影響など前述の考慮事項について柔軟に対応できるカーボンプライシングとして、キャップ&トレード型の排出量取引制度は、タイミングも含め日本の実情に即した適切な制度設計ができれば、有力な選択肢となるとしている。*「国内排出量取引制度」とも。温室効果ガスの排出量取引制度の一つ。企業に排出枠(限度)を設け、その排出枠(余剰排出量/不足排出量)を取引する制度。今後の対応としては、CN行動計画等の着実な実施、「GXリーグ」の推進を行うとともに、「きめ細かな配慮」が必要となる「キャップ&トレード型の排出量取引制度についての検討」、この3つの対応を同時に実施すべきとする。これらの対応の中で「キャップ&トレード型の排出量取引制度についての検討」については、少なくとも当初はすべての対象排出主体について、目標達成していれば排出対価を負担しなくても良い仕組み、いわゆる「無償割当」*1により制度を開始すべきとしている。また「きめ細かな配慮」については、業種・企業ごとのBAT(削減技術と時間軸)を考慮した削減目標の適切な設定(透明性・公平性を確保)、産業競争力維持、とりわけ国際競争に晒されるHard-to-abate産業*2等への特別な対応のあり方(「無償割当」の取扱い等)、政府による民間の事業活動への過度な介入への懸念払拭、エネルギーの安価安定供給、対象となる事業所の範囲などが挙げられている。*1:いわゆる「無償割当」であっても、排出目標を超過して排出した企業には、その超過排出量に見合うだけの排出枠を他企業から購入する義務が課される。そのため、企業は排出目標を超過しないよう、削減ための投資を自らの負担で行うこととなる。*2:現段階において、脱炭素化が困難な産業部門・エネルギー転換部門。GXリーグの積極的な推進と排出量取引制度の知見の蓄積については、「GXリーグ」は、経済社会システム全体の変革のための議論と「新たな市場の創造」のための実践を行う場として極めて有意義とし、政府はMRV(排出量の測定・報告・検証)に関するルール整備を含め、この取組みを全力で推進すべきとする。資料では、経済界としても「GXリーグ」に積極的に参加する意思を表明するとともに、「GXリーグ」における実践を行う中で、政府においてキャップ&トレード型の排出量取引制度に関する知見・ノウハウの蓄積を図り、排出量取引制度に発展させることが可能かどうかの検討を行って欲しいとの要望も出している。(続く)
MaaS・CASE関連の最新ニュース(2 / 65ページ目)
「50万円以下で買える新車」が値上げ! 「宏光 MINI EV」が値上げした背景とは 他
5月30日 昨日は経団連が発表した「グリーントランスフォーメーション(GX)に向けて<概要>」についてから、昨今話題となる「グリーントランスフォーメーション」(GX)とは何かを探って来た。本日はその第2回目となる。資料中には、2050年CN(カーボンニュートラル)を実現するために必要な方策(GX政策パッケージ)の中にある「CN実現に向けた諸政策」の項目中に、エネルギー供給構造の転換があり、基本的な考え方や、電源の脱炭素化及び電力ネットワークの次世代化について言及されていた。本日は次項目となる熱・線量の脱炭素化(カーボンフリー水素・アンモニア・合成燃料等の導入)から追いかけたい。産業向け熱需要をはじめ、熱量的・経済的に電化が難しい領域については、水素やアンモニア、合成メタンを活用して脱炭素化を図るとする。産業・民生部門における熱・燃料の脱炭素化は、2030年度に向けてLNG等の低炭素エネルギーへの転換・利用の高度化、水素・アンモニアの利用、カーボンニュートラルLNG(クレジットでオフセットされたLNG)の活用を図るとしている。2050年を見据えては、水素・アンモニア、合成メタンの社会実装・安価安定に向けて、必要な技術開発、国際的なサプライチェーンを構築するとしている。運輸部門における燃料の脱炭素化については、資料に割かれるスペースが多い。◆自動車については、各国のエネルギーを取り巻く状況や、自動車部門におけるそれぞれの脱炭素技術の適性・用途を踏まえ、「電動化や既存の内燃機関」の活用に向けた技術開発に取組み、あわせて「EVステーション・水素ステーション」の整備の加速化、内燃機関での水素や合成燃料(e-fuel)、バイオ燃料等の活用に向けた技術開発・供給体制の整備に取組む。◆航空機・船舶・鉄道については、持続可能な航空燃料(SAF)の実用化に向けた研究実証、アンモニアの船舶用燃料としての利用に向け研究開発等に取組む。次には「原子力利用の積極的推進」が上がる。原子力は3Eのバランスが取れた電源(S+3Eではない)とされ、エネルギー安全保障の観点からも極めて重要とされ、核融合を含め引き続き日本が強みを発揮できる分野とされる。現在10基が再稼働済み(停止中含む)だが、2050年23基、2060年8基のみ(60年運転)となる。安全性の確保を大前提に積極活用していく方針を明確化すべき、まずは既存の設備を最大限活用していく視点が重要としている。最新の科学的知見を国民に示し、理解を得、技術・人材の観点から猶予はないとする。政府として早急に新たなプラントの建設方針を示すべきとしている。2030年度に向けては、既設発電所の再稼働と設備利用率の向上、安全性を大前提とした運転期間の60年への延長の円滑化や規制の合理化(運転期間延長、不稼働機関の除外を含む)、新規制基準への適合性審査の迅速化を進めたいとする。2050年を見据えては、60年を超える運転期間の検討、安全性が向上した革新軽水炉に加え、SMRや水素製造に活用できる高温ガス炉等も念頭に置き、政府として新たなプラントの建設方針を示すとし、核融合は我が国こそ積極的に取組み実現すべき技術と位置付け、具体的ロードマップを示し、国家プロジェクトとして研究開発に取組みたいとする。核燃料リサイクルの確立、最終処分の実現といったバックエンドへの対応について、事業者の不断の取組みとともに、国の積極的な関与が必要としている。国内原発の現状を把握して頂くための参考まで。公益財団法人ニッポンドットコムが運営する nippon.com の「日本の原子力発電所マップ2021年版」によると、福島第一原発の事故から10年を経た2021年3月時点で、日本国内で稼働している原発は9基(何れも加圧水型)で、西日本に集中している。東日本大震災の発生前、国内の原発は54基。日本で使用する電力の約30%を賄っていたとされる。震災以降に廃炉が決定した原発は21基だ。資料中の「参考」では、原子力発電の設備容量の見通しについては、2030年度エネルギーミックスにおける原子力比率(20%=約27基分)を実現しようとする場合、約2700万kWの設備容量(発電電力量約1900億kWh)が必要とされる。*設備容量:発電設備における単位時間当たりの最大仕事量。発電電力量:発電設備がある経過時間に供給した電力の総量。2050年段階で原子力比率を10%(=約20基分)または20%(=約40基分)に維持しようとした場合、同資料中の図表にプロットした設備容量が必要となる(参考:https://www.keidanren.or.jp/policy/2022/043_gaiyo.pdf *資料18頁)。*2050年の発電電力量は1.4兆kWhと想定。40年運転を60年運転に延長したとしても、2050年に23基、2060年では8基のみ稼働が可能な状態となると試算されるとしている。ちなみに原子力発電所の長期運転による発電費用(IEA試算、2019年、稼働期間に係る総費用を総発電電力量で割って算出)では、陸上風力が最も高く17.7円/kWhとなり、原子力(長期運転)が最も割安で5.1円/kWhと表わされている。ちなみに、陸上風力、太陽光、洋上風力は何れも費用がかかるとされ、従来の石炭火力、ガス火力はその中間となる。ちなみに原子力(新設)の場合は、ガス火力と拮抗しており、12.4円/kWhとなる。ちなみに資料には記載がないが、エネルギー安全保障を前提としつつも、昨今のウクライナ情勢を鑑みるなら、原子力発電は有事に日本や周辺国に対するリスク要因となり得る点は付記しておきたい。電化の推進・エネルギー需要側を中心とした革新的技術の開発については、エネルギー供給構造の転換と併せて、エネルギー需要側においても、省エネ・電化、イノベーション、グローバル・バリューチェーンなどの面で幾つかの対応が求められるとする。省エネ・電化の面では、更なる省エネ(ヒートポンプや電熱線等の電化製品の普及を促す)、家庭やオフィス等の電化を加速し、電化率の向上を図ることが求められる。イノベーションの面では、エネルギー需要側におけるイノベーションを加速する観点から、強力な支援策の展開や投資環境の整備を図ることが求められる。多様な技術のポートフォリオ等、様々な道筋の想定も重要。グローバル・バリューチェーンの面においては、グローバル・バリューチェーンを通じた削減、すなわち原料調達・生産・使用・廃棄・リサイクル等のライフサイクル全体(LCAの視点)での削減を後押しすべきとしている。期待されるエネルギー需要側のイノベーション(でありアクション)とは、◆生産プロセスの変革、革新的製品・サービスの開発・普及例として、「産業部門」では、鉄鋼業における水素還元製鉄の実現など、主要産業における製造プロセスの抜本的な変革等、「運輸部門」では、環境性能に優れた自動車・船舶・航空機・鉄道車両の導入、「自動車においては技術中立的な形での電動化や燃料対策等」が、「民生部門」では、既存を含む建物・住宅の高断熱化・ZEB/ZEH化・電化・BEMS/HEMSの導入の推進等が期待されている。その他、◆材料におけるカーボンリサイクル、ケミカルリサイクルの推進や、◆ネガティブエミッション(DAC*1や生物機能利用と、貯留または固定化等を組み合わせることにより、正味としてマイナスのCO2排出量を達成する技術)としては、森林吸収源対策、DACCS、BECCS*2が期待されている。*1:DACとは、大気中のCO2を直接捕集する技術。*2:BECCSとは、バイオマスエネルギーの燃焼により発生したCO2を捕集・貯留する技術。また、2050年CNを実現していく上で重要なキーワードとなる「グリーンディール」(主に政府による投資方面の意味合い)については、2050年CN実現のためには、同年まで継続的に巨額の投資が必要とされ、累計で400兆円程度(IEA/World Energy Outlook 2021によれば、2050年CNに必要な世界の年間総投資額は4兆ドル、日本の必要投資額を対世界でのCO2排出割合3%に基づき、計算すると約14.2兆円/年となる)にも上ると試算される。これについて経団連は、政府に民間の継続的投資を促すため、自ら中長期の財政支出をコミットし、時間軸(技術・政策)を付したロードマップを明示すべきとし、欧米の事例を踏まえ、日本で必要となる政府負担は約2兆円程度と試算している。このための財源として「GXボンド*」の発行等で賄うべきとする。*CNに向けたトランジション及びイノベーションに関する技術の開発・社会実装に使途を限定し、GX実現のため発行する国債のこと。「グリーンイノベーション(GI)基金」(10年間で2兆円)は、企業の研究開発投資を後押しするものとして評価するも、民間のリスクテイクの補完や、対象としてカバーする範囲、社会実装・商用化まで視野に入れた規模等の観点で不十分とし、研究開発への支援策に限っても、現行と同規模の基金を再び組織する必要があるとする。民間企業がとるべき施策として、積極的な研究開発投資・設備投資に取組んだり、自らの需要拡大の取組みも検討して欲しいとする。政府がとるべき施策としては、①リスクの大きい革新的技術開発や、水素サプライチェーン等の大規模なインフラ整備などへの投資、②民間投資促進のインセンティブ(研究開発税制の拡充、規制改革等)、③新たな技術等の社会実装・普及の促進、国際的に公平な競争環境の整備に向けた支援制度、投資回収の見込めるスキームの整備、産業用の電力・水素にかかるエネルギーコストなどのオペレーションコスト面の支援も重要としている。次頁の参考にある「2050年カーボンニュートラルに向けた投資額」(IEA試算)によると、2050年CN達成に必要となる2030年までの年間の総投資額は、世界全体で約4兆ドル。世界に占める日本のCO2排出割合(3%)に応じて分配すると、必要年間投資額は約14.2兆円となり、2050年までに引き直した場合(2022~2050年の29年間)の累計投資額は、約411.8兆円としている。また重要なキーワードの一つとなる「サステナブル・ファイナンス」(ファイナンス:主に財源や資金、金融や融資の意味合い)では、我が国のCN実現に向けた必要投資額は莫大なものとなり、国内外のESG資金(約4200兆円)を取り込むべきと提言。また、アジア全体での莫大なGXの資金需要が見込まれる中、我が国がアジアにおける「サスティナブル・ファイナンス」機能の中心としての地位を確立すべきとしている。事業者には、GXへのコミットメントとそれに向けた戦略を開示し、実行することが求められ、投資家等には、建設的な対話・評価を行い、効率的に資金供給をすることが求められている。政府には、GXに向けたグランドデザインを示し、国際ルールと整合する形で情報開示や評価に関する基盤整備を進め、市場機能を強化したり、トランジションの主流化に向け、国際的な基準作り・ルール形成等において、米国・アジアなどとも連携しつつ、主導権を発揮して欲しいとする。整理すると、2050年CN達成に必要となる2030年までの年間の総投資額は、世界全体で約4兆ドル。世界に占める日本のCO2排出割合(3%)に応じて分配すると、必要年間投資額は約14.2兆円となり、2050年までに引き直した場合(2022~2050年の29年間)の累計投資額は、約411.8兆円となる。「グリーンイノベーション(GI)基金」(10年間で2兆円)では不足する。財源は国内外のESG資金(約4,200兆円/35.3兆米ドル)の取り込みとなる。これによりアジアにおけるサステナブル・ファイナンス機能の中心としての地位確立を目指すという文脈だ。(続く)
EVワイヤレス走行中給電を実証へ—電界結合方式 他
5月27日 この5月18日に経団連の十倉雅和会長が萩生田光一経済産業大臣を訪問し、「グリーントランスフォーメーション(GX)に向けて」を建議し、GXを巡り意見交換を行った。また5月24日に東京で開催されたクアッド首脳会合で岸田首相が国内総生産(GDP)とは別に「グリーンGDP」を新指標として整備する方針を示した。近くまとめる経済財政運営の指針(骨太方針)を盛り込み、脱炭素社会を目指すものだ。これとあわせ「安全最優先の」原発再稼働に向けた取り組みも明記される。経団連は「グリーントランスフォーメーション(GX)に向けて<概要>」を5月17日に発表している。日本政府は、2020年10月「2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする」と宣言し、この達成目標を成長機会と捉え、産業競争力を高める考えだ。この流れの中、2022年2月に経済産業省は経済社会システム全体の変革(GX:グリーントランスフォーメーション)を牽引する「GXリーグ基本構想」を公表し、本格稼働に向け2022年度中に実証事業の準備を進め、2023年4月以降の本格導入を目指すとしている。話題の中心となる「グリーントランスフォーメーション」(以下:GX)とは何か?経団連は「グリーントランスフォーメーション(GX)に向けて<概要>」の資料をめくると、まず「気候変動を巡る状況とGX」との項目が目に入る。序を含め、おさらいしてみたい。経団連は「サスティナブルな資本主義を掲げる」が、今日行き過ぎた資本主義により、生態系の崩壊や気候変動が叫ばれる。前述の通り日本は世界に対して、2050年にカーボンニュートラル(以下:CN)、2030年度に46%削減をコミットしている。国全体の取組みとして「経済と環境の好循環」を果たし、グリーントランスフォーメーション(GX)を推進する必要がある。また昨今のウクライナ情勢を受け、エネルギー安全保障を確保するため「構造転換」が必要とされる。経団連は政府に「GX政策パッケージ」をまとめるべきだと提言、前述の資料には「リプレース・新増設を含む原子力利用の積極的推進」、「グリーンディール」、「カーボンプライシング」などについて、経団連としての、現時点での考えが示されている。経団連は岸田政権と「軌を一に」し、GXをサスティナブルな地球環境の実現を基礎に据えつつ「投資主導で経済拡大を目指す成長戦略の中核」と位置付け、産業競争力の強化と同取組みにおける国際社会のリードを決意、我が国のGX実現に向けた取組みを加速させるとしている。気候変動問題を巡る状況とGXについては、自然災害の多発・甚大化など年々厳しさを増しているため、危機感を持ち早急な対応が必要とし、2050年CNや2030年46%削減はチャレンジングだが、覚悟を持ち取組むべき課題と捉え、これには経済社会全体の変革=GXが不可欠だとする。実現のため、国内投資の必要と成長戦略に組み込み、持続可能な成長につなげる必要があるとする。しかしこの過程には大きな社会変革が伴う。「産業の構造転換の影響を受ける労働者」や「追加の国民負担(電力コストの上昇など)」は避けて通れない。国民の理解の醸成が必要とされる。欧米に比べ、気候変動問題に対する国民の意識は高くないとされるため、政府が国民を啓発、理解を得るべく(2050年CNを目指す意義、目指す経済社会、エネルギー構造の将来性、サーキュラー・エコノミ―等関連政策との関係等)に分かりやすい説明を尽くすべきであり、その際「CNの過程で生じるコストの社会全体での負担の在り方」についても正面から議論すべきとする。参考資料として上がる「大気中のCO2濃度」によると産業革命(1760年代~1830年代)前に280ppmだったCO2濃度は、上昇を続け、2018年現在で400ppmに達した(Point of no return)。これが450ppmを超えると臨界点を迎える。これを回避するため、2050年に向け様々な技術の実装に取組み、CNの実現を目指す。目標とされる一次エネルギー供給量の構成は、化石燃料(85%)、再エネ(12%)、原子力(3%)とされ、最終エネルギー消費量の構成は、材料(35%)、熱源(38%)、電力(27%)+ロス(発電等)とされる。電力についてはゼロエミッション電源の確保(再エネの主電源化、原子力の積極的推進、脱炭素火力の実現)、電化の推進、次世代電力ネットワークの実現、熱源については熱源へのカーボンフリー水素・アンモニア・合成メタンの導入、材料については材料におけるカーボンリサイクル、ケミカルリサイクルの推進の実装を目指す。これらに加え、すべての分野で生産プロセスの変革、革新的製品・サービスの開発・普及、またネガティブエミッション(森林吸収源対策、DACCS:大気から直接炭素を回収・貯留する、BECCS:バイオエネルギーを使って炭素を回収・貯留)などの対策が加わる。日本CO2排出量(2020年、電気・熱配分後)は、全体で10.4億トン(内訳:エネルギー起源CO2が92.6%、非エネルギー起源CO2が7.4%)産業部門が34%、運輸部門が17.7%、業務その他部門が17.4%となり、世界のエネルギー起源CO2排出量(2019年)は336億トン、中国が29.4%、米国が14.1%、EU28ヵ国が8.9%、日本は6位で3.1%となる。2050年CN実現に向け、イノベーション、トランジション、投資の促進、産業競争力強化の視点が必要とされる。うちイノベーションでは、要素技術開発(10年)プラント実証(2~3年)、社会実装(3~4年)、建設・チューニング(1~2年)とされ、計約20年の時間が必要とされるため、2050年から逆算すると今すぐ取組む必要がある。移行期にはBAT(例:省エネ、高効率なLNG・石炭火力、原子力などの技術)の最大限の導入等、既存のあらゆる手段を総動員すべきとしている。経団連が政府に求める「GX政策パッケージ」は、原子力利用の積極推進、電化の推進・エネルギー需要側を中心とした革新的技術の開発、サステナブルファイナンス、カーボンプライシング、攻めの経済外交戦略、産業構造の変化への対応、グリーンディール、エネルギー供給構造の転換等を、先の技術の社会実装とともに政策のロードマップの明示、司令塔の確立を行い、官民の投資を最大限引き出し、産業の国際競争力を維持・強化すべく、「GX政策パッケージ」のグランドデザインを早急に提示すべきとしている。司令塔には、GXに向けた投資促進のため、中長期の政策動向や、投資回収に関する予見可能性の確保が求められる。必要となる技術、投資額、政策に関して時間軸を付したロードマップを明示すべきとしている。司令塔には内閣総理大臣を議長に、関係省庁の町および産業界・学術界の有識者をメンバーとする「GX実現会議(仮称)」の創設を求めている。CNに向けた諸政策には、①エネルギー供給構造の転換(エネルギーミックスの実現と電力システムの次世代化)、②原子力利用の積極的推進(既設原子力の最大限の活用、リプレース・新増設、SMR・核融合等のイノベーション)、③電力の推進・エネルギー需要側を中心とした革新的技術の開発、④グリーンディール、⑤サステナブル・ファイナンス、⑥産業構造の変化への対応、⑦カーボンプライシング、⑧攻めの経済外交戦略等が挙がる。①では「安全性、安定供給、経済性、環境」(*S+3E)を大前提に、エネルギー供給構造の転換、自給率向上、調達先の多角化が必要、移行期においては原子力をはじめ、既存技術の最大現活用が求められるとしている。「地理的制約・エネルギー資源に乏しい日本の置かれた状況を踏まえる必要あり」とする。続く資料では、太陽光発電は適地となる平地面積が少ない一方、平地面積当たりの太陽光発電の設備容量では、主要国中最大であること、化石燃料、原子力、再エネの特性比較では、原子力は純国産、ゼロエミッションに適合、約12円/kWhの経済効率性としている。原子力の発電特性としては、長期固定電源(定常的な需要の一部を賄う)と表されている。続く電源の脱炭素化および電力ネットワークの次世代化では、電力は相対的に脱炭素への道筋が整うが、2050年CNを実現する「適切な電源ポートフォリオ」(一般にポートフォリオは投資家の保有する金融商品の一覧や組合せを指し、どの種類の資産にいくら分配し、その資産の中でどの銘柄をどれくらい買うか、を考えること)の実現、「次世代電力ネットワークの構築」が鍵とされ、電源ポートフォリオの検討にあたっては、電源等リソースそれぞれの特性を考慮した適切なバランスが模索されるべきであり、再生エネルギーの大量導入を支える基幹系統の再設計、分散化を加速する需要地系統の高度化を並行して進めることが必要とされている。再生可能エネルギーの主力電源化では、再エネの地理的制約を踏まえ、低コスト、安定供給、責任ある事業規律を備えた「主力電源」として最大限の導入を図るとする。2030年度に向けては、競争力獲得が見込まれる洋上風力や屋根置き太陽光の導入、地熱の開発加速等に係る環境整備に官民のリソースを集中、再エネ比率36~38%実現に向け、S+3Eを大前提に規制改革を含む政策強化を実施すべきとしている。2050年を見据え、技術開発と普及、事業環境整備に足元から取り組む必要があるとする。火力電力の脱炭素化については、調整力・慣性力・同期化力を有する現在の主力電源とし、火力発電の今後の活用・CO2の排出を伴う火力電力の「脱炭素化」に係るロードマップの明確化・対外的な発信の必要性が解かれている。2030年度に向けては、S+3Eを大前提にLNG等の低炭素燃料への転換を進め、非効率火力の廃止を進めつつ、依存度を低減するとし、2050年を見据えては、水素・アンモニアの混焼から、専焼、CCUS(Carbon dioxide Capture, Utilization and Storage:分離、貯留したCO2の利用)に係るイノベーションを創出としている。*CCS(Carbon dioxide Capture and Storage:CO2回収・貯留)は含まれていない。次世代電力ネットワーク(再エネのグリッド網、蓄電機能等)の確立については、再エネの大量導入に向けた系統整備、分散化を加速する配電ネットワークの高度化を並行して進め、既存インフラを維持・更新して行くための投資を確保するとし、ローカル系統・配電系統については、送配電事業者がそれぞれの再エネ導入量を想定してプッシュ型の系統構築を効率的に進めるとしている。また、レベニューキャップ(コストダウンの成果を事業者利益とすることを認めることにより、事業者に効率的な経営へのインセンティブを与える制度)を中心とした新たな託送料金制度を適切に運用するとしている。多くの変動制電源を電力システムに統合していくため、「EV(電気自動車)」を含めた蓄電池・揚水発電等の蓄電設備を活用するとしている。(続く)
韓国LGが自動運転コネクテッドカーの実車を披露、6GとAIを駆使 他
5月26日 鉄道経営の「ひっ迫」がメディアで盛んに報じられる。特に「地方鉄道」の存否に関わる問題が議論されている。各地域のインフラを担う鉄道の価値を、単に運賃収支だけで赤字路線とし廃線議論に直結させてはならない。新型コロナ感染症の影響で人々の移動が制限されたつづけた結果である近年の決算を元に、議論するのは時期早尚と映る。観光をはじめとする、宿泊業や飲食、小売業などの回復状況を見ても、新型コロナ感染症の影響が低減し、社会の移動需要が回復をみて、本質的な問題と言える人口減少する地方という経営環境の下で、移動需要を持続的に活性化できる施策を打ったのち、決算をもとに「地方鉄道」の存否を議論すべきだ。例え地方鉄道を「バス転換」しても、公共交通機関としての「体」を延命するだけで、それだけでは本質的に地域の移動に資する、経済環境の再構築や移動需要の喚起には繋がらない。5月11日に28道府県の知事が厳しい運営が続く地方鉄道の在り方を、国に問うた緊急提言がその表れと言えよう。一方で、鉄道会社も手を拱いているわけではなく、地元球団のラッピング列車を走らせたり、地元産品を使った「ぬれせんべい」を販売したり、有名人とコラボレーションを図ったり、地域交通を維持するため、鉄道とバスが連携する等の動きも始まっている。JR四国と「徳島バス」は、今年4月から四国の徳島県南部の一部区間で、共同経営を開始している。これまで独占禁止法により制限されていた鉄道とバスの経営協力など、新たな体制作りで再起を図る(バス会社同士の共同経営を認めるという同法の特例法の適用をJRにも拡大、国交省の認可にこぎ着けた)。鉄道会社の自社保有する鉄道車両の活用から、鉄道の持つ「機能」に着目した取組みがある。5月25日「JR東日本」と「ENEOS」は、2030年までの社会実装を目指し、水素ハイブリッド電車(JR東日本 FV-E991系「HYBARI」)と、FCV(燃料電池車)向け定置式水素ステーションの開発を進めるとしている。水素ステーションでは、水素ハイブリッド電車をはじめ、燃料電池車やFCバス、FCトラック等の車両、駅周辺設備などにも「CO2フリー水素」(*CO2を排出することなく製造された水素)を供給する。具体的には、ENEOSの拠点より、JR東日本の川崎火力発電所にCO2フリー水素が供給され、同発電所で水素混焼発電による電力供給を目指すという。この記事自体は、鉄道事業とエネルギー事業の知見を活かしたCO2フリー水素サプライチェーンの構築、脱炭素などの話題で書かれたものだ。地方では永く「モータリゼーション」が定着し、これからも住民の日常生活の足を支えるのは、電車ではなくクルマであることは変わらないだろう。ガソリン車時代、クルマの航続距離の発達は都市間の移動のニーズを、鉄道からクルマに移し、また地下鉄サリン事件の後、しばらく鉄道車両のに棚が使われなくなったように、新型コロナ感染症が残した、換気が行き届かないという意味の閉鎖的空間を心理的に避けたい利用者が、自家用車での移動を選択するようになったため、本来、高速で大量輸送を得意とする鉄道は機能不全を起こしている。(*最近では、窓開けが推奨されるだけでなく、一部鉄道会社の車両には、空気清浄機能が設けられ始めている。)しかし、これからの事情に新たな「変数」が加わる。モータリゼーションの立役者、自動車は燃料をガソリンに求める従来車から、FCV(燃料電池自動車)や、電気自動車(EV)への置換えが急速に進むだろう。一方で、地方では従来のガソリンスタンド(SS=サービスステーション)の後継者難などにより、急速に「SS過疎」が進む。私たちは「赤字ローカル線」「移動需要創出」「地域経済」「脱炭素」「持続的社会」「SS過疎」など、「移動」についての複雑なパズルをどう解いていけばいいのだろう。日本の鉄道の電化率は67%と言われる。残りの33%は「非電化区間」となる。ウクライナ情勢を見ても、ロシアが鉄道施設や駅を盛んに攻撃する理由の一つに、鉄道が兵器の輸送や兵器燃料の補給手段であることが挙げられる。鉄道が都市に対して持つ機能には、旅客輸送以外にも、貨物輸送機能やエネルギーの輸送機能との側面がある。日本の鉄道貨物輸送は、主にJR貨物や各地の臨海鉄道、セメント・石灰石や沿線の特定の需要企業のための民営鉄道により支えられており、年間4,394万トンもの物資が線路上を行き来している。うち70%はJR貨物が担い、残り30%は臨海鉄道やそのおh化の民鉄が担っている。JR貨物が線路上で運ぶのは、食料工業品(342万トン)、紙パルプ(267万トン)、宅配便等(264万トン)、農産品・青果物(177万トン)などだ。また車扱の輸送実績(894万トン)の約7割は石油類が占める。特に臨海部から内陸部への輸送には、鉄道が多く使われている実態がある。*参考:車扱輸送とは、コンテナ輸送と大別し、タンク車など貨物1両単位で化し切って輸送する形態。石油輸送が7割を占めるが、大型変圧器の輸送や車両メーカーで製造された新型車両の鉄道会社への納入などもこれに当たる。このように、鉄道はエネルギー輸送媒体としての側面(機能)がある。アビームコンサルティングは「鉄道業界における異業種参入のトレンドと今後の方向性」(https://www.abeam.com/jp/ja/topics/insights/railroad_industry)として、インサイトを発表している。アフターコロナにおける鉄道会社の運輸事業は、事業の抜本的な構造改革の必要に迫られており、運賃見直し、減便、終電繰り上げ、生産性向上のためのDX、チケットレス化、ワンマン・自動運転の拡大、IoTなどテクノロジーを活用した予知保全(CBM・スマートメンテナンス等)の推進が加速すると予想され、収益拡大に向けては、マイクロツーリズムの観光需要拡大、地方におけるワーケーション需要の喚起等新たな需要創出が加速すると見込まれるとしている。非運輸事業では、シェアオフィスなど駅や駅周辺におけるサービスの拡充、駅周辺や沿線の魅力あるまちづくりなどが挙がる。また非接触型の交通系ICカードの浸透ににより、利用者の移動・購買・決済に関わるデータを鉄道会社が活用できる機運も高まるとしている。鉄道会社の異業種参入例としては、観光喚起、インバウンド喚起、ワーケーション、デジタルPF(プラットフォーム)、シェアオフィス、EC、魅力的なまちづくり、DX効率化、自動運転、MaaS、カーボンニュートラルなどが挙がる。魅力的なまちづくりを方針として掲げるのは、JR3社に対し、民鉄が8社と民鉄の関心が高い。反対に観光喚起はJR5社に対して、民営が2社、ワーケーションはJR4社に対して、民営が1社と民営の割合が少ない。デジタルPF(プラットフォーム)はJR 0社に対して、民営5社と民営の関心が高い。ECは3者とも民営だ。各社の路線が走る地域性や、各社の成り立ちなどにも拠るところもあろうが、各社の方向性の違いは興味深い。鉄道事業の新たな異業種参入は大別すると、①進出先業界の業法改正への対応、②社会動向の変化対応とに整理できる。①にはキャッシュアウト事業、エネルギー小売り事業への参入があり、キャッシュアウト事業は、「銀行法の改正」を受け沿線利用者が券売機で現金の引き出しができる仕組みの構築と展開を図っている。「エネルギーの小売り事業」では、「電力事業への市場参入規制の緩和(電力の自由化)」を背景に沿線顧客に対して、自社のポイントサービスや他生活サービスを組み合わせた事業展開を行っているとのことだ。②次に社会動向の変化への対応として、MaaS推進事業やシェアオフィス事業への参入が挙げられる。MaaS推進事業では、都市部における交通渋滞や環境問題、高齢化・過疎化する地方部の交通弱者の問題等を見据え、鉄道会社がタクシーやバスなどの他の運輸事業者と連携したシームレスな交通サービスの検討・展開を進めている。シェアオフィス事業では「働き方改革の推進」を受け、遊休資産等を活用したシェアオフィスの設置による沿線価値の向上と事業機会の創出の場の提供を行っている。異業種参入の契機は異なるものの、いずれも鉄道会社が所有するアセット(発券機、沿線顧客、鉄道会社の持つ公共性・信頼性のブランド力、自社の運輸サービス、交通系アプリ、遊休資産など)にデジタルを融合することで、事業の実現性を高め、新規収益獲得への寄与を企図している。JR東日本とENEOSが新規投資を必要とする「定置式水素ステーション」を考えるなら、鉄道会社は既にあるアセットの活用も考えたい。赤字ローカル線にあたる地方の「非電化区間」の車両を「移動式蓄電池」と見立て、車両から取り出した電力を、駅でBEV(電池で駆動する仕組みを持つ電動車両)向けの電力としてを販売できないか。欲を言えば、この電力は「CO2フリー水素」で発電した電力、JR東日本の川崎火力発電所のような施設で大量生産(コスト安)されたものであることが望ましい。まさに、これから始まろうとする「モータリゼーション」の電動車(EV)化による電力需要を見据え、EV用や災害時の電力として、あるいは地域産業や観光需要向けに販売することは出来ないか。電化区間で充電した蓄電池を載せ、非電化区間で運用するJR東日本のEV-E301系のようなハイブリッド車両の蓄電池容量を増強し、赤字ローカル線(非電化区間)に投入、長時間停車する駅や、都心から見て終着側となる車庫における滞泊時間を利用し、駅構内に設けた蓄電池に蓄電する。「鉄道駅」は、もともと街の交通結節・集客の役割を担ってきた。従来からある「パークアンドライド」の概念も世に浸透し、MaaS事業に取組み、自治体運営のバスなどのEV化も見込まれる。駅前に駐車場を整備できれば、今後利用が増えるであろうEVバスやEVタクシー、ラストワンマイルに利用可能な小型モビリティの充電スポットとして機能させることは、そう難しいことではないものと思われる。どれだけ山間地域であったとしても、駅は観光客など、外部からの訪問者が利用する充電スポットとして、この上なく分かりやすい立地にある点も大きい。もとより鉄道車両は、同じくエネルギーを運ぶタンクローリーなどと比べ小回りは利かない分、輸送能力が高い。線路さえあれば「定置式」ではなく「移動式の給電装置」として利用出来るため、地域を管轄する電力会社のエネルギーマネジメントシステムと繋ぎ、各地の需要がある駅で利用することも出来る。災害時などに自治体の需要に合わせ、需要次第では編成を長大化することも出来る。もし「赤字ローカル線」である区間が、電化区間ならば、既に電車用の架線が張られているため、蓄電/給電装置だけ用意できれば、蓄電車両を仕立てる必要もない。「駅」というアセットの価値を見直し、新たな用途で活用し直すことが可能なら、駅は地域の充電スポットとして、「赤字ローカル線」を持続させる新たな財源になり得るかもしれない。マンションや個人宅における充電設備の普及までには、まだ時間がかかる。交通機関が維持・利用されるためには、その基盤となる堅調な通勤や通学需要などとともに、地域経済自体が観光などが活性化されなければならない。電力と電力を利用した鉄道・駅の組合せは、地域の周遊を活発化させる可能性を持つ。歴史的に見ると、電力会社と鉄道会社は強い結びつきがあったことを見ても、両事業の親和性は高い。電力会社自身が鉄道を運営していたり、反対に鉄道会社が電力を販売していた例も存在したようだ。現在も、例えばつくばエクスプレス(首都圏新都市鉄道株式会社)などは新電力事業者として、東京電力への売電を行っている。東急電鉄の子会社「東急パワーサプライ」も、2016年4月から家庭向け電力小売事業に参入している。「地方鉄道」の存否が盛んに取り上げられるが、国やメディアが議論し具体案を掘り出すべくは、交通機関の経営状態以前に、その基盤(ベース)となるコロナ禍後の経済に即した「規制の見直し」や「地域経済の復興・開拓」の具体案ではないだろうか。
京セラ、自動運転社会に向けた技術を公開–死角情報を可視化、シミュレーターで体験 他
5月25日 5/24に国土交通省で開催された「第7回 交通分野におけるデータ連携の高度化に向けた検討会」に伴い、中間とりまとめ(案)の概要が発表された。昨日は交通分野における「データ連携の高度化」に向け、資料中でポイントとされる「チケッティング」と「リアルタイムデータ」のうち、「チケッティング」について書かせて頂いた。本日はもう一方の「リアルタイムデータ」についてお話したいと思う。リアルタイムデータのデータ連携に向けた課題を大別すると、ビジネス面と技術面での課題に分かれる。ビジネス面から俯瞰すると、利用者の視点では動的データは、静的データと比較し連携の優先度が低いとされ、整備や外部提供に伴う費用対効果や、小規模事業者の視点では整備にかかる費用面、人材面でのリソース不足、またデータ連携を行う場合、企業間での条件調整の負担が大きいとされる。技術面では、現状のデータ整備状況に視点が置かれ、鉄道分野では既に同データがホームページやアプリ、駅構内などの情報提供に利用されており、整備が進む。バス事業者でも一部事業者では「バスロケ」による位置情報の公開や、GTFS-RT(動的バス情報フォーマット)での整備が進む。フェリーや船舶分野では、一部事業者でホームページ等に運行情報を提示しているとの状況が示され、課題としては、リアルタイムデータの単独活用は難しく時刻表・ダイヤ情報との紐づけが必要となるため、表記等を統一する必要があるのと、他社乗り入れを行っている事業者は車両が自社のものだけではないため、すべての車両のデータを公開・活用できないケースがあるとされた。事業者は、利用者の利用シーンや交通モードにより、必要な情報が正確でタイムリーに提供できることが望ましいとする。定常時においては運行・運航情報、到着予測時刻に対するニーズがあり、災害時などにも輸送障害が発生した場合、コロナ禍における三密回避やイベント時開催時等において、混雑情報の必要が認められると考えている反面、動的データは静的データと比べ優先度が低いことから、データ入手に伴う費用対効果が得られるかが重要とされた。上記コストの積算方法として、トランザクションに応じた方法や、各社個別に総額が設定される方法などが考えられるが、データ利用する場合は、その積み上がる総額で計算する必要があるとする。また、利便性だけでなくデータの正確性等、その情報提供に伴うリスクや責任にも留意の必要があるとしている。利用者がリアルタイムデータで、最も利用するのは「運行情報」及び「出発・到着予測情報」とされ、情報を一つの場所で閲覧でき、より新しい情報が求められる。特に災害時や運休・遅延時に、ホームページやアプリ等で迅速に情報を入手したいとのニーズがある。「データの連携体制」については、リアルタイムデータの連携や流通を促進するため、①データの価値や正確性、信用性、意味合いを担保する仕組みが必要だが、②各社が個別に交渉を行うと契約事務コストが大きく、③リアルタイムデータの外部提供する際のセキュリティ対策、データ利活用に伴う責任分界、④小規模事業者などでデータが未整備である場合、データ生成や外部提供のためのシステム構築等にかかるコストや人的リソースが不足する点などの克服が求められる。まずは、円滑にデータ連携を行う仕組みと、運用体制を構築することが効率的と考えられる一方、そのような仕組みや運用体制を構築する場合、既存データのフォーマット変更やシステムリプレイス等により、現状以上のコスト負担が生じることになる点や、持続性を確保するための収益構造や運営方法が課題とされた。データ連携基盤には、競合他社を含む様々な事業者が使用することが想定され、データのコントロール・条件設定の仕組み、データ利用者による具体的なデータの使われ方を踏まえ、データ連携基盤に求められる要件の検討・見直しが必要と締めくくられている。「データAPIの共通仕様の必要性や整備・提供に伴うコスト等」については、「データ形式・APIの共通仕様の必要性」として、データ形式だけでなく、特徴や制限事項、表記や運用ルールが示され、リアルタイムデータについては、基本敵にAPI連携が想定されるため、APIの標準化またはデータ連携基盤におけるAPI仕様が公開されることが望ましいとされ、バス事業におけるGTFS-JPとRTのように、リアルタイムデータは静的データと組み合わせ使用することを念頭に置き、突合しやすくする必要があるとしている。「データの整備・提供に伴うコスト・責任分界」については、各事業者におけるリアルタイムデータの整備は、利用者の利便性向上が目的であるため、必ずしもデータによる収益が求められるものではないされている。一方で本データを受け、ビジネスを行う事業者に対しては、整備に要したコストがあるため、相応の負担を求めたいとの意見もある。また、リアルタイムデータの外部提供については、データ提供先におけるデータ活用方法のコントロールがし辛くなり、その「本来的な意味や意図から離れた利用」も懸念されるとする。また、データの信頼性や遅延なども想定されるため、責任分界の明確化が必要とされている。「データ提供における費用の考え方」については、データ量や情報量、利用者数等の従量課金、事業者ごとの個別金額が想定されるが、データ利用者の観点では、積算された費用の総額に着目した検討が必要とされる。一方でトランザクション数や利用者を収集できる仕組みや、データ利用者側からの報告の仕組み等を構築する必要がある点にも留意が必要とされる。データ提供に対する対価として、データ利用者側に蓄積されるデータなど、金銭的なもの以外も存在するのではないか、としている。これまでの検討を踏まえた概括では、データ連携高度化の意義と、①「既にMaaSに取組んでいる、プラットフォーム開発などに着手済みの事業者」と、②「これからMaaSに取り組むプラットフォーム開発などに未着手の事業者」、「双方の共通事項」に分けて内容がまとめられていることなどから、検討会は、全国で「チケッティング・リアルタイムデータ」を必要とする事業者を、利用者の多寡、経営環境、取組みの結果、事業者が得る報酬の大小、標準化/共通化コストの考え方、導入による影響、事業者の保有するデータベースの価値、外部提供した場合の影響などの観点で、①②をグループに分け、双方の事情に適した「データ連携の高度化」に道筋を付けようと考えている様子も伺える。また、①②双方にデータ連携の意義や重要性が認められ、データ連携が行いやすい状態が形成されていることが望ましいが、前述した課題や懸念を上回る効果は「未だ見えづらい」としている。様々な事情を考慮し「データ連携」のあり方としては、広くエリア(地域)や(交通)モード、事業者を跨いで行われるのでなく、「必要となる一定の事業者・エリアの中において、モードを越えて行われる」ことがよいとしている。分野ごとの方向性や論点として、総論としては、デジタル化へのインセンティブが小さい事業者にフォーカスを当てた国の取り組みが求められるとした一方、既に「データ連携」が行われている事業者の取組への影響という観点から、エリア、交通モード、事業者を跨いで、広く共通化、標準化することには慎重な姿勢を示し、昨今の観光や移動需要の減少を考慮する必要があるとしている。「チケッティング」については、手法そのものの統一化ニーズは少なく、様々な手法が存在する前提において、地域特性、利用者属性などエリアの性質、顧客接点、商品造成など競争性の高い部分を阻害しない手法間の連携を検討、既存システム/機器の改修・リプレイスに伴うコスト負担、不正利用防止対策、セキュリティ対策についての一定の基準や、トラブル発生時の責任分界については検討の必要を示した。「リアルタイムデータ」については、データ整備に係る費用、人的なリソース確保、データ提供に係る費用とその負担の在り方、データの正確性・信用性・意味合いを担保する仕組みや責任分界、データ形式やAPI仕様、その取扱いについてを引き続き検討する必要があるとしている。2日間にわたり交通分野における「データ連携の高度化」について取り上げさせて頂いた。中間とりまとめ(案)の概要からは「コスト」「責任分界」「システム構築の手間」「個社のシステム整備状況」「個社の経済状況」など、重要な論点が山積している状況が分かる。導入が進みづらい主な理由として挙がる、事業者視点で「データ連携」によりサービス品質は向上するが、費用対効果が合わない点(データ利用者からの収入で採算が採算ベースに乗るか)などは、情報インフラを利用してもらう通信関係者に利用料を広く分散する知見を求めるのはどうか。また、契約事務コストの低減などは「電子契約プラットフォーム」等を利用することで、多少でも事務負担軽減し、契約を迅速化に繋ぐことも出来るものと思われる。経済産業省の四国経済産業局が、この5月20日に取りまとめた「令和3年度四国地域におけるMaaS等の新たなモビリティサービスに係る調査事業」の中で、JR西日本と邑南町が地域にキャッシュレスや買い物のデジタル化、病院受付とモビリティサービス連携タクシー事業者への配車システム導入による統一フォーマットでのデータ収集などの事例では、「地域ごとの交通事情が異なるため、システムやアプリが地域に特化されている場合が多いことを挙げ、単純に転用が出来ない点、地域ごとに地域専用のMaaSシステムを構築するのは費用的に困難である点を挙げ、基幹となるMaaSシステムのオープン化と、API(地域に必要なサービスとの)連携の推進」との意見も示されている。課題の幾つかは、短い期間でも情報収集にリソースを集中することで、早期解決に繋ぐこともできるのではないだろうか。*アイコン画像:フリー素材ぱくたそ(www.pakutaso.com)
大阪メトロ、次世代移動「MaaS」前進 バス→車いす→病院など アプリで一括予約目指す 他
5月24日 国土交通省では、新たなモビリティサービスであるMaaSの基盤となるデータ連携のあり方について、リアルタイムに変化する運行情報や予約・決済情報等の動的なデータの連携・利活用の高度化を推進し、予約・決済、さらには実際に(モビリティを)利用するまでをシームレスにすることの意義や必要性、課題等の取りまとめを目的に、有識者や交通事業者で構成する「第7回 交通分野におけるデータ連携の高度化に向けた検討会」を、本日5/24に開催する。これに伴い、中間とりまとめ(案)の概要が発表されている。国交省では、MaaSパイロットプロジェクト等への支援を実施し、日本各地で「MaaS」というキーワードで様々な取り組みが行われる中、各取組みの推進のため、MaaSの特徴である「シームレスな移動」の実現に向け、意義や課題、今後の方向性を検討する。特に既に高度で利便性の高い公共交通等が提供されている日本において、これまでのハード・ソフト両面の蓄積を活用しながら、交通分野におけるデータ連携の高度化との観点で検討が行われる。検討会は、各種機器等の導入・リプレイス等を考慮し、今後最長で15年程度を見据えるとしている。シームレスな移動の実現に向け、重要と考えられるのは、チケッティング(チケットのデジタル化と多様な利用手法の連携等)とリアルタイムデータ(動的データ、即ち遅延・運休などの運行情報、ロケーション情報等)だ。なぜ、チケッティングやリアルタイムデータに重きが置かれるのか?チケッティングに関する情報からは、公共交通や移動サービスを利用するための"手法"が把握できる。現在は鉄道やバス等の日常的な利用では、交通系ICカードが普及する傍ら、MaaSなどの新たな移動においては、スマートフォンの画面表示、QRコード等の二次元コードを使用したチケット等、多様な手法が出現している。今後、利便性を維持・向上するためには、単一の手法の場合と比較し、相対的に(複数の手法の)連携の必要性が高まることが考えら、チケットに係るデータが媒体間、事業者間で連携されていれば、利用者のシームレス性を担保、向上できると考えられるという。また、リアルタイムデータは利用者が移動する際の情報として活用する各移動サービスのリアルタイム情報であるが、リアルタイムデータは時刻表等の静的な情報と組合せて使用することで(*)、事業者やモードを跨いだ移動をシームレスに行う(提供する)ことに寄与する。現在は各事業者は、遅延・運休等の運行情報を駅やバス停、ターミナルや自社のWebサイト・アプリ等で提供しているが、これらの連携を促進することにより、利用者の移動をよりスムーズかつシームレスにできると考えられる。検討会は、公共交通を含めたシームレスな移動の実現等により、公共交通の利用拡大や生産性向上等を通じた、持続的な公共交通の実現に向け更なるデータ連携・利活用の推進に向けて、知見や課題を共有、整理したいとする。チケッティングの連携に向けた課題と論点は、望まれる絵姿としてサービス利用に要する時間を少なく出来る等、利用者の利便性向上に繋ぐことや、連携拡大による移動需要の喚起や連系手段を構築し、様々な意義を事業者・利用者の双方にもたらし、生産性向上に繋ぐこととされる。利用者にはチケットに対し、利用可能エリアや有効期限の種類拡大やインターネット上での購入のニーズがあり、チケットは紙媒体を介さずスマホ上で利用し、都度アプリを切り替えることなく、一つの手段で全ての交通機関を利用したいなどの期待がある。しかし、エリアごとに利用者の年齢構成や公共交通の整備・利用状況等の地域特性があり、モード毎に利用頻度や単価、予約の要否等が異なる。また安心・安全な利用のため、不正利用防止策やセキュリティ対策などが課題として挙がる。また駅員や乗務員の負荷軽減や無人駅での利用を考慮し、目視ではなく機械処理可能なチケッティング手法が必要とされる。利用が多い駅では、処理速度や安定性が求められ、既存システム・機器のリプレイスには多大なコスト負担がかかる。これらのチケット導入の際も、手数料や収益分担、トラブル発生時の責任分界についても連携する業者間で調整が必要となる点などが挙げられた。リアルタイムデータの連携で望まれるのは、乗り継ぎの効率化等のサービスの高度化は有効とされたが、費用対効果を高める仕組み、事業規模の大小に拠らずデータ連携によるメリットを享受できる仕組みとして行くことや、利用者への情報提供に止まらず、収集したデータを通じて、業務効率化や環境負荷軽減、健康増進等、各社・各所の様々な便益に繋ぐなどだ。利用者には運休・遅延・到着予測・出発予測情報へのニーズがあり、通勤時や災害発生時、出張や旅行時、またその計画を立てる時、乗換時や、様々な気象条件下で待ち時間を過ごす時、運行本数が少ない路線を利用する時、イベント時、荷物や子連れ、体調不良などの際、これらの情報が利用されることが分かっている。これらリアルタームデータの連携を実現するため、提供者側では費用対効果が見合うか、小規模な事業者にとってはデータ整備に係る費用や人材の不足、データ連携を行う際、個別の企業ごとに条件調整を行うのは非効率、データの正確性の担保、データ提供に伴う責任分界の明確化が必要などの点が課題となる。データの利用者の立場では、リアルタイムデータを時刻表やダイヤ情報と紐づけた上で提供して欲しいが、通信頻度が高くなり、データ利用料が増えるとサービスが利用し辛くなってしまう。改札や運賃箱などの機器は、今後10~15年程度、システム等のソフトウェアは最短で5年、長いものでは15~20年程度かけたリプレイスや導入を見据える。検討会は手法の連携については、事業者に裁量が留保された中立的な手法で統一された状態が、利便性の向上やコスト削減の観点からは望ましいが、すでに手法が確立しているところもあり現実的には困難、地域により特性が異なるため、既存の手法や取組みを前提に、手法を跨いだ連携方法の検討が必要としている。モード間の連携については、モード毎にその性質に応じてシステムが構築されることから、コスト負担が小さいかたちでそれらを連携する仕組みが必要とし、モード毎に利用の頻度や単価、予約の要否も異なる点も考慮が必要としている。エリア間の連携については、利用者の年齢構成、公共交通の整備、利用状況、地域特性が異なるため、全国規模ではなく、一定のエリアごとに連携拡大する方向を示し、観光客が多いエリア等、エリアによっては他のエリアからの流入(客)が多い場合もある、そのようなエリアでは全国的な連携も検討が必要、都市部と地方部という観点では、連携していることが望ましいものの、上記の通り性質が異なるため、慎重な検討が必要としている。手法の連携については、一定のエリア内で、そのエリアに適した手法を用いて事業者間の連携等を深めていく方向性が想定され、引き続き議論が必要としている。チケッティングの技術面での課題としては「デジタルチケットが備えるデータや規格」については、多様になると対応が増えるため統一化が望ましいが、一方で設備更新等の新たなコスト負担が発生したり、チケットの料金設定や利用可能エリアの多様性などが失われてしまうことも懸念され、チケット発行については自由度を持たせつつ、チケットの認証等で処理できる仕組みが理想としている。鉄道については、既存の連絡運輸の枠組みを尊重して対応、偽造防止対策・不正利用防止対策、セキュリティに対しては一定の基準があることが望ましいとした。また「デジタルチケットの利用媒体や手法」については、現場の負荷軽減や無人駅などでの利用を考慮し、機械処理が可能な手段が望まれるとともに、利用者の多い駅などでは交通系ICカードや、別の手法だとしても、交通系ICカードと同程度の処理速度、安定性等が望まれるとし、将来的に新技術の登場なども織り込んだ見通しが必要としている。またトンネル内や山奥等の電波環境が悪い状況出の利用可能性にも考慮が必要とした。「データの活用」面については、将来的にはデジタルチケットの利用を通じ、出発地から目的地までの移動に関わるデータが得られることが理想としている。チケッティングのビジネス面での課題については、「コスト削減と利用者・関係者への対応」では、紙チケットのコスト削減、駅業務効率化、利用者の利便性向上に期待するも、システム構築やリプレイスに伴うコスト負担を懸念、全面的にデジタル化が進行した場合、スマートフォンを利用できない人への対応や子供料金等への対応等に不安があるとしており、またチケット販売車には、旅行代理店も含まれることから、すべてデジタル化することはかえってコスト負担が大きく、旅行代理店等との調整・システム連携が必要としている。「手数料・収益分担」面では、チケットの条件等について、事業者間での調整が必要とされ、収益分配の方法が重要、利用実績に基づく分配などが想定される都の意見がある一方、実績データ収集のためのシステム及び現場運用にかかるコストや、事業者の規模等を考慮したコスト配分の実施対する不安なども挙がった。チケット販売において収益化を見込む場合は、手数料などで得られる収益と、システム構築などに伴うコスト増などのバランスの見極めが重要とされている。「トラブル発生時の責任分界」については、チケット利用における不具合への対応、交通事業者とチケット販売事業者との責任分界点が事業者によって異なる場合があるため、一定の方針があることが望ましいとされている(続く)。*参考:https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport/content/001477661.pdf
近距離モビリティのWHILL、トヨタ子会社ウーブングループから資金調達 他
5月23日 経済産業省の四国経済産業局が、5月20日に「令和3年度四国地域におけるMaaS等の新たなモビリティサービスに係る調査事業」の報告書を取りまとめた。報告書は、四国地域におけるMaaS等の新たなモビリティサービスの普及・啓発のため、同県が「令和3年度無人自動運転等の先進MaaS実装加速化推進事業(四国地域における新たなモビリティサービス産業創出及び周辺関連産業との連携可能性調査及びスマートモビリティチャレンジ地域シンポジウム四国開催事業)」を行ったことによる報告となっている。内容は四国地域内の取組みに係る包括調査、先進地ヒアリング調査、MaaS普及に向けたシンポジウム開催など。事業は高度経済成長とともに進展したモータリゼーションが、少子高齢化の影響で地域の交通サービスや移動の縮小など、様々な問題が顕在化して来た中で、政府は「未来投資戦略 2018」により、「MaaSの実現等により新たなモビリティサービスのモデル都市・地域を構築する」とし、交通事業者を含む民間事業者によってもMaaS関連の取組が始まっているとし、この調査により四国地域全体にMaaS等に関する検討や取組みを波及させることを目的とし、①まずは、四国島内におけるMaaSの先進事例ついて調査したとしている。②この次には先進事例を四国島内に普及させるため、関心のある事業者や自治体に声をかけシンポジウムを開催、③シンポジウム内にてMaaS等に関心のある参加者と、MaaSに取り組む事業者をマッチングさせ、次の(新たな)展開を期待するものとしている。包括調査については、四国経済産業局と伊予銀行/いよぎん地域経済研究センターが連携、管内の実態把握のため、文献やインターネット検索、関係者への取材調査を行い、調査対象エリアをリスト化、4エリアを選定、さらに調査対象エリアを2ヶ所に絞り、現地ヒアリングを実施している。またグリーンスローモビリティ事業については香川県琴平町を選定している。ヒアリング調査では、上記以外、四国管外にもヒアリングを行うとともに、シンポジウムでの事例紹介などを依頼、調査内容は四国経済産業局に提出されている。シンポジウムでは管内・管外の計6ヶ所(島根県邑南町(おおなんちょう)、富山県朝日町、新潟市、香川県三豊市、琴平町、松山市中島地区)のヒアリング策より2ヶ所を選定、事例紹介を行っている。同シンポジウムは、四国総合通信局、四国運輸局、四国地方整備局も参画し、伊予銀行地域創生部、いよぎん地域経済研究センターなどの協力を得て開催されている。シンポジウム開催までは、計画の立案や課題整理の段階から、開催まで約8ヵ月という短期間で計画が勧められている。包括調査における調査対象には、三豊市・三豊市社会福祉協議会、㈱電脳交通、㈱伊予鉄グループ、久枝地区(松山市)まちづくり協議会が含まれる。四国島内グリーンスローモビリティ調査(ヒアリング調査)では、松山市中島地区、三豊市、土庄町(とのしょうちょう)、琴平町、東かがわ市、香川県三木町、高知県四万十市等がリストアップされたが、調査時点でも活動中であった香川県琴平町が選ばれている。ヒアリング調査は、「移動課題解決」や「地域活性化」の視点から地域特性を踏まえ、地域住民のニーズ対応を図る取組、既存の交通サービスを活かして地域の社会課題を解決する先進的取り組みやロールモデルとなり得る取組みの抽出に目的が置かれ、詳細な事項(課題)を調査し、社会実装に向けた課題整理や、対応策の検討につなぐものとした。ヒアリングの内容としては、市町村名、事業・プロジェクト名、【地域交通の課題】、事業の推進体制、事業実施時期、【事業・プロジェクトの内容】、利用実績(アプリDL数、登録者数、決済件数、金額など)、【事業の効果】、利用者の完走・意見、【普及・定着に向けた課題】、今後の方向性、【他サービスとの連携可能性】、自動運転車両等の導入可能性、【MaaS推進に当たって国や産業界への意見・要望など】が設定された。新潟市の件では、参画したNEC㈱、新潟交通㈱、日本ユニシス株、富山県朝日町の件では㈱博報堂など民間企業にもヒアリングが実施されている。管外のヒアリング先であり、2018年4月1日にJR三江線が廃止された、島根県邑南町を例に地域交通の課題を見てみると、邑南町の利用者視点では、交通路線の縮小や廃線による利便性の低下、自宅と目的地がバス停と乖離。計モノや病院への動線と公共交通が連動していない。スマホの保有率が低くデジタル参入へ障壁が高い。事業者視点では、きめ細やかなバス運行を確保するための費用増、運営主体の廃業、NPOによる運営の安全確保、高齢化、効率化、行政視点では既存路線の維持、代替交通確保による費用増、縦割り行政、部署間連携が取りにくい、交通と観光の施策が連動していないことなどが挙がる。同町はこれらの課題に対し、JR西日本、特定非営利活動法人はすみ振興会、㈱電脳交通との推進体制を組んだ。JR西日本は、社内に「MaaS推進部」を設置し、地方型、観光型、都市型におけるMaaS展開を通じ、管内の移動をシームレスに利用してもらう社会の実現を目指し、取り組みを開始。旧三江線沿線の地域とコミュニケーションを継続、同社のMaaSに対する取組み方針を邑南町に伝え快諾を得たとし、2020年4月から同町と「地方型MaaS」に3ヶ年計画(同月から2023年3月まで)を組み、実証を行うこととした。実証内容は、地域公共交通のデジタル化とキャッシュレス化、町内観光素材(鉄道資産・A級グルメ)との連携や情報発信、生活関連サービス(病院・スーパー等)との連携、都市エリアとのつながりとしており、その構築を試みている。具体定には、NPOにデマンド型タクシー「はすみデマンド」(登録車両:32台)を運行することとし、配車システムや(電話も含む)予約システムを構築、町内バス、タクシー、自家用有償旅客運送で使える地域カード(「さくらカード」)を展開。町内の37店舗でICOCAの利用を可能としている。また、同町の旧三江線の駅舎を鉄道公園として整備、京都市にある梅小路ハイライン(鉄道高架上の京都屋台ストリート)で、邑南町フェアを開催、またJR西日本の観光型アプリ「setowa」で同町の観光素材を掲載するなど情報発信も行っている。生活関連サービス(病院・スーパーとの連携)では、町内で買物が困難な住民に移動販売を行う店舗にヒアリングを実施、病院・スーパー間などで利用できる移動サービスの連携の在り方を検討している。都市エリアとの繋がりを確保するため、町内のバスデータを更新し、都市エリアから邑南町内の目的地まで、経路検索を可能としている(JR西日本の「WESTER」/「setowa」上で実現)。これら事業の効果として、邑南町とNPOは、情報通信技術を活用した「地方版MaaS実証実験」に参加し、課題発見や技術導入の知見を学ぶことが出来る環境を得たが、利用者は電話予約が主となり、利用者、運転手ともに、タブレットやスマホの使用に抵抗感があり、機器を使うまでの(心理的)障壁の高さがあると感じているという。今後の課題として、①デジタル化やキャッシュレス化の部分では、配車Webフォームの実用化し、観光客への訴求も検討する、デジタル化により取得されたデータの有効活用、ICOCAを使ったキャッシュレス路線・店舗の拡大を図る。②また情報発信については、町内観光素材をPRする効果的なエリアと手法を選定したり、NPO江の川鐡道の観光支援などを行うとしている。③生活関連サービスについては、買い物支援(移動販売等)のデジタル化、病院受付とモビリティサービス連携、見守りサービス連携などを図る。④都市エリアとのつながりの面では、広島エリアからのアクセス向上を目指す。広島駅から三次駅まで移動した後、同駅からは備北交通の路線バスで移動、自家用有償旅客運送(はすみデマンド)に繋ぐ経路や、観光客のはすみデマンド利用の可否などを検討する。またMaaSアプリ「setowa」と連携、デジタルチケット販売を検討する。NPO法人は、人口が少ない地域においてはサービス提供者も限られるため、「※将来的に幅広いサービスを担う可能性」を想定、限られた人材で効率よく複数のサービスを、統括し提供できるシステムを必要としている。他サービスとの連携可能性の部分では、JR西日本と邑南町は、LSI社との連携によるキャッシュレス化(「さくらカード」による決済)、買い物支援のデジタル化、病院の受付とモビリティサービスの連携、タクシー事業者への配車システム導入による統一フォーマットでのデータ収集などが挙がる。MaaS推進にあたって国や産業界への意見や要望の部分では、JR西日本は地方エリアは人口密度が低く、高齢化が進み、サービス事業者は少ないため、地域交通と生活サービスの利便性の向上と業務の効率化は必要、交通面では、定時路線型など従来の手段では地域のニーズにそぐわなくなっており、抜本的な見直しに向けデジタル等のハード及びその根拠となる法規定の柔軟な整備が必須となる。主に「高齢者のデジタル化対応力の向上」、「事業者のデジタル化への負担軽減」への支援を要望しており、邑南町とNPOは、全国でMaaSが研究されるものの、地域ごとの交通事情が異なるため、システムやアプリが地域に特化されている場合が多いことを挙げ、単純に転用が出来ない点、地域ごとに地域専用のMaaSシステムを構築するのは費用的に困難である点を挙げ、基幹となるMaaSシステムのオープン化と、API(地域に必要なサービスとの)連携の推進を要望として挙げている。(*参考:https://www.shikoku.meti.go.jp/01_releases/2022/05/20220520b/20220520b.pdf)国土交通省では、令和4年5月13日に「第4回 鉄道事業者と地域の協働による地域モビリティの刷新に関する検討会の開催について」が開催されている。同検討会は、各地の地方ローカル線が沿線人口の減少や少子化、マイカーへの移転などを受け、利用者が大幅に減少する等、一部区間は危機的な状況に置かれており、新型コロナウイルス感染症の影響の長期化で(利用者減少に)拍車がかかっていると状況を説明する。同検討会は、こうした鉄道路線の現状について鉄道事業者と沿線地域が危機認識を共有し、改めて(鉄道の)大量高速輸送機関としての特性を評価した上で、相互に協力・協働しながら、利用者の利便性と持続性の高い地域交通「再構築」の必要性を説く。同会は今年2月に立ち上がり、夏ごろの取りまとめに向け議論を推進するとしている。先に参考として上げた「令和3年度四国地域におけるMaaS等の新たなモビリティサービスに係る調査報告書」には、邑南町を含めた地域の貴重な取組みや、実証の結果得られた貴重な知見が集約されている。検討会の関係者には、ぜひ一度目を通していただきたい資料だ。また邑南町のNPOが課題として意見を挙げた中に、「(地域のNPOが)将来的に幅広いサービスを担う可能性」との言葉がある。NPOの活動には、未だ形式知化されていない地域のニーズが集約されている可能性がある。新たな移動に関わる経済創出の源泉という見方は出来ないだろうか?
日産自動車、三菱自動車、NMKVが新型「軽EV」のオフライン式を実施 他
5月20日 「特殊車両通行確認システムの不具合への対応について」。国土交通省のウェブサイトに掲載された報道発表資料のタイトルだ。特殊車両の道路の通行に関して、通行可能経路を指定するシステムの運用を4月1日から始めたが、今回のシステムの不具合についての説明は「システムにエラーがあることが判明したので発表いたします。誤ったシステムを用いて特殊車両が通行可能との回答を出したことにより、特殊車両を通行させる申請者の方々をはじめ、関係者にご迷惑をおかけし、深くお詫び申し上げます。」となっている。詳細となる別紙には、1.事案の概要について、2.プログラムの誤りの内容について、3.誤って道路の回答を行った件数、4.対応件数、5.今後の対応について記載されている。事案は令和4年4月から運用開始した特殊車両通行確認システムについて、プログラムの誤りにより、本来通行できない車両の通行を認めていたことが、5月12日になって判明したという。同システムは、国土交通省関東整備局が、株式会社建設技術研究所と日立製作所へプログラムの開発業務を発注し、作成されたものとのこと。一般財団法人道路新産業開発機構が、このシステムを用いて、利用者に通行可能経路の回答などを行っている。同機構は、特車新制度の業務(車両の登録、通行可能な経路の確認等)を実施する一般財団法人として、道路法に基づき国土交通大臣が指定した指定登録確認機関だ。また、プログラムの誤りの内容については、特殊車両通行確認システムは、特殊車両を通行させる運送会社等の申請者が、通行させる車両の重さや長さ、車両の種類等(ばら積みの貨物を運搬できる車両かどうか等)を自ら登録し、即時に車両が通行できる経路を自動で検索して許可証と同等の効力を持つ回答書を作成するシステムだ。経路検索に際しては、例えばばら積み貨物を運搬する車両の軸重が10トンを超える場合は経路検索を行わないなど、車両の種類に応じて、システムが自動的に検索を行う上限値が定められているという。今回の不具合は、ばら積み貨物を運搬する車両等について、その上限値を超えていないことを確認するプログラムが搭載されていなかったために、発生したとする。このプログラムの誤りにより、誤って行われた経路の回答は、今年の4月1日から5月12日まで、480件、73社に上る。このうち107件、23社に対しては上限値を超えたにも関わらず、本来不許可となるべき申請について、通行可能であるとの誤った回答が出されていた。5月12日にシステムエラーが判明した後、誤った回答書が発行されたすべての申請事業者(23社)に、翌5月13日に走行の中止の要請が行われた。しかし、このうち2社は中止の要請が間に合わず、走行したことが確認されたため、再度走行の中止を要請したという。5月16日時点では、すべての事業者に走行の中止をして貰ったという。また回答書の再発行のため、事業者に連絡し条件変更等の対応をしているという。走行中止を要請した23社の対応状況は、新たに回答書を再発行(16件)、同予定(1社)、事業者から再発行は不要との回答があった(4社)、事業者と引き続き回答書の再発行の調整中である(2社)となる(5月20日現在)。なお。回答書が八呼応されえた4月以降に、誤った回答書に基づく走行があったかどうかは、国交省が現在確認中とのことだ。このシステムは、5月18日に、今回の不具合となったプログラムが改修された。同省は、今後の再発防止に向け「特殊車両通行確認システム」について、今回の誤りに限らず「照査」を改めて実施するとしており、運送会社等の利用者に陳謝した。一般財団法人道路新産業開発機構が、ホームページ上で特殊車両通行確認制度について「道路行政セミナー・4月号」の道路法令Q&Aで、制度を説明している。これによると特殊車両とは、道路法(昭和27年法律第180号)第47条第1項及び車両制限令(昭和36年政令第256号)に規定された、一定の基準を超過した車両のことを言い、またの名を「限度超過車両」という。例えばダブル連結トラックやトレーラーの一部などが、この特殊車両に当てはまるという。経済産業省資料によると、構造又は貨物が特殊な車両(特例8車種・新規格車・海上コンテナ)については、①特例8車種には、バン型セミトレーラ、タンク型セミトレーラ、幌枠型セミトレーラ、コンテナ用セミトレーラ、自動車運搬用セミトレーラ、あおり型セミトレーラ、スタンション型セミトレーラ、船底型セミトレーラ(タイプⅠ)、②新規格車は車両の構造が特殊なもの、前面などに「20t超」のステッカーが貼付されている車両、③海上コンテナは貨物が特殊なもの(国際海上コンテナ用セミトレーラ)などが挙がる。道路法第47条第2項においては、原則として特殊車両による道路の通行は禁止(車両でその幅、重量、高さ、長さ又は最小回転半径が前項の政令で定める最高限度をこえるもの*は、道路を通行させてはならない。)されているが、特殊車両の構造と道路の構造の関係に照らして、当該車両が支障なく通行できる場合もあり、そのような場合一定の手続きによって特殊車両が通行できることになっている。*「一般的制限値」は、高さ3.8m(*指定道路4.1m)、長さ12m、幅2.5m、最小回転半径は12m、左右の輪荷重5t、軸重は10t、総重量20t(*指定道路25t)、一般的制限値を一つでも超える車両は、道路管理者の通行許可または通行可能経路の回答が必要とされる。同じく道路法47条の2に規定されている「特殊車両通行許可制度」により、道路管理者は車両の構造や車両に積載する貨物が特殊であるため、やむを得ないと認めるときは、当該車両を通行させようとする者の申請に基づき、必要な条件を付した上で、通行を許可することが出来るとされる。しかし、従来は道路を通行したい者が行う申請ごとに、道路管理者が毎回許可の手続きを行っていたため、この手続きに時間を要していたという。通行許可に至るまでの審査にかかる時間は、令和2年度においては、平均約24日。「ドライバ不足に伴う車両の大型化の進展により」許可の件数自体が増加していることなども、許可が下りるまで時間を要する一因となっていたとのこと。こうした現状に対応するため、「道路法の一部を改正する法律」(令和2年法律第31号。以下「改正法」という。)の改正規定の一部が令和4年4月1日に施行され、特殊車両が道路を通行するにあたっての新しい制度が創設された。これが「特殊車両通行確認制度」だ。この制度は、国土交通大臣が、特殊車両の通行できる経路の有無を確認し、特殊車両を通行させようとする者に対して通行可能な経路を回答する制度のことだ。改正法によって新設された道路法47条の4から第47条の13までの条項に規定される。「許可」とは異なる手続きにより、特殊車両の通行が可能になるが、事前に特殊車両を登録する必要がある。登録をする際には、車両情報や車両の重量を把握する方法等を入力する必要があるが、1度登録してしまえば、以後5年間に亘って「確認制度」を利用することが出来る。車両の重量を把握することで、重量制限を超過した大型車両が、道路や橋に与える悪影響を未然に防ぐ役割を果たす。登録車両を通行させようとする者は、道路法第47条の10 第1項に規定される通り、高度交通大臣に対し、通行可能な経路の有無の確認をすることが出来る。この確認に対し、国土交通大臣は直ちに確認の結果として、当該経路の有無および通行が可能である場合は、具体的な経路を回答することとされている。ただし、登録車両はETC2.0車載器を搭載したものに限られ、通行可能経路の確認の対象道路は道路情報が電子化された道路に限られる。(「特殊車両通行確認制度/システム」は)従来の「特殊車両通行許可制度」と比べ、圧倒的に早い時間で限度超過車両の通行可能経路が分かるようになる。この裏舞台では、道路法47条の13に規定される「データベース」が整備されているからだ。データベースの中身は、特殊車両の登録事項や通行可能経路の判定基準、確認の求めに対する回答実績などがあり、これらに基づいてオンラインシステムにおいて即座に回答をだせる仕組みが構築された。今後も「特殊車両通行許可制度」は、「特殊車両通行確認制度」と併存する形で残るという。しかし、特殊車両通行確認制度は、①「早い」(即時に通行経路を確認可能)、②「簡単」(一同登録するだけで、オンラインシステムを利用して自動的に経路を検索できる)、③「便利」(複数の経路を一度に確認することが出来る)の3点において、従来の制度よりも使い勝手の良い手続きに進化している。今回の「特殊車両通行確認システム」については、システムの根幹となる「データベース」のさらに根幹となる情報である主な車両諸元(軸重、隣接軸重、輪荷重、総重量)のうち、例えば軸重における本来の上限値は10トンであるものの、誤った回答により平均12.2トン、最大20.2トンの車両の走行が許可されていた。スタートダッシュこそ上手くいかなかったが「特殊車両通行確認システム」は、DXの流れに沿った「便利で良いシステム」だと思う。この「データベース」は、自動運転やカーナビの経路案内、高精度地図やV2Xにも様々な場所にも転用出来そうだ。現在の道路事情を多方面から俯瞰し、今後の改善や利便性向上に繋げて頂きたい。だが、「法とプログラム」の間に横たわる今回のミスは、自動運転に取り組む企業でも起こる可能性がある。当該システムに限らず「データベース」を運用する際、基礎情報を「どのように確認していくのか」は非常に重要な点だ。まして自動運転システムの関係ともなれば「確認」の重要性は飛躍的に高まる。そうだとすると「確認・照査」による予防は、新制度を創設・運用する側の関係省庁や団体が対応すべき喫緊の課題と言えるのではないか。
中国「自動運転タクシー」の商用運行に正式許可 他
5月19日 4月24日に中国の広東省広州市南沙区で小馬智行( Pony.ai / ポニー・エーアイ )がタクシー事業の営業許可(自動運転タクシーの商業許可)を取得した。同国内で、自動運転タクシーの商用運行が正式に許可を得たのは、同社が初めてということになる。ポニー・エーアイは、まず100台の自動運転タクシーを投入、5月から800平方キロメートル(*余談だが、宮城県栗原市の面積が804.97平方キロメートルで、今回のサービスエリアとほぼ同面積である。東北新幹線の「くりこま高原駅」を擁する同市は、菅原文太氏が青春時代を過ごし(*旧:栗原郡一迫町)、みなみらんぼう氏の生まれ故郷(*旧:志波姫町)でもある。)のエリア内でサービスを始めるとした。広州市南沙区は、1993年7月に広州南沙経済技術開発区として設立され、2005年4月に広州市南沙区となっている。総人口は75.17万人。ポニー・エーアイは、2016年に設立された中国の自動運転のスタートアップ、自律運転技術開発と自動運転タクシーサービスを行い、トヨタ自動車、中国第一汽車集団、広州汽車集団など主要なOEMとパートナーシップを結ぶ。昨年(2020年)秋の時点で、中国では自動運転タクシーが営業運行直前の段階まで、駒を進めていた。営業開始は、2022年の北京冬季オリンピック前後と予想されていた。中国では、自動運転タクシーが営業運行(有料)に至るまで、自動運転タクシー事業者に「6段階のステップ」が義務付けられているとされていた。1.閉鎖区域による試験走行→2.公道による試験走行→3.モニターを乗車させる試験営業→4.誰でも乗車可能な全面開放試験営業→5.常態運行による無料試験営業→6.有料営業運行)となる。正式営業に至る段階では、サービスによる利益創出の仕組みが課されるとの内容であったと思う。同自動運転タクシーサービスは、PonyPilot+アプリを介してタクシーを呼び出し、料金の支払いも行う。料金は一般のタクシーと同額に設定されたようだ。運行は8:30~22:30となる。運転席には、安全担当者の登場が義務付けられているところを見ると、自動運転タクシーサービスについて、市側もまだ自動運転タクシーサービスに対して、慎重な姿勢は崩していない様子も伺える。ポニー・エーアイは、今後中国国内の北京市や上海市、深圳市などで、同じく商用運行を始める計画で、広州を含むこれらの都市と、米国カリフォルニア州でも自動運転タクシーのテストを進めている。広州市で自動運転タクシーのライセンスを取得するためには、中国またはその他の国で24ヶ月間、100万キロ以上の自動運転を実施し、広州市が定める地区で20万キロ以上の自動運転テスト走行を無事故で走り抜き、国家検査機関が定めた厳格な安全性およびその他の様々な車両認定テストに合格する必要があるようだ。ちなみにポニー・エーアイが、2018年12月にリリースした同社の自動運転タクシーアプリを利用した利用者の、2022年4月時点の注文完了数は 700,000件以上とされ、その8割近くが同サービスをリピートしているという。日本では、4月21日にホンダモビリティソリューションズ㈱と、帝都自動車交通、国際自動車の3社が、2020年代半ばから東京都心における自動運転モビリティサービス(こちらは、自動運転タクシーサービスではなく、自動運転モビリティサービス/オンデマンド型無人移動サービスと表現されている)の展開を目指し、関連法令やサービス設計、事業者間の役割、責任分担のあり方などについて検討するため、基本合意書を締結している。ホンダは、本モビリティーサービス(「クルーズ・オリジン」を使用した自動運転モビリティサービス)の展開に向け、昨年(2021年9月)に、GMクルーズホールディングスLLC、ゼネラルモーターズ(以下、GM)と共同で栃木県宇都宮市・芳賀町で2022年から公道実証を実施すると発表している(技術実証は2021年9月から開始)。当初、着手されたのは自動運転車両の走行準備として、地図作成用の車両を用いた高精度地図の作成だった。地図の準備が整い次第、自動運転車両「クルーズAV」による公道走行を通じて、日本の交通環境や関連法令に合わせた自動運転技術を開発・検証するとしていた。また、その事業運営は、ホンダモビリティソリューションズ㈱が担うとしていた。ここ最近はホンダが、本サービスについて次のニュースを発表してくれるのを、いまか今かと待っているような状況ではないだろうか(ソニーの「VISION-S」と似た状況だ)。思い直して同社のホームページにその情報を求めると、当初、Hondaテストコース内での地図作成に着手、技術実証を行っていた時分からの情報が手に入る。自動運転技術の「日本適合化開発」にあたっては、自動運転モビリティサービス事業日本適合化開発プロジェクトの技術責任者である、波多野 邦道氏と、担当である有吉 斗紀知氏へのインタビューも公開されている。波多野氏は、ホンダが自動運転モビリティサービス事業を行う意義としては、「日本において自動運転を活用したモビリティサービス事業を展開することになるが、これは日本社会の発展や社会課題の解決に大きく寄与できるのではないかと考えている。大きくは3つの観点があり、①まずは社会的な観点。新しい移動手段の提供により、日本の都市の活性化や、地方の交通課題の改善・解決につながると考えている。②次に重要なのは、安全面。自動運転というシステムはヒューマンエラーをなくしていくことを期待されるので、より安全で自由な移動を実現して行けるのではないかと考えている。③最後に大事なのは、環境になる。今回の車両はEVをベースとして活用していくので、移動の効率が上がり、最終的にはカーボンニュートラルに大きく貢献して行けるのではないかと考える。」とし、「同時に『すべての人に生活の可能性を拡げる喜びを提供する』というホンダの2030年ビジョンがあるが、ここで掲げている「移動」と「暮らし」を、新しい価値の創造という形で目標を達成したいと考えている。これを確実かつ強力に新しい事業へ取組んで行きたいと考えている。」としている。Cruise社との自動運転技術の役割分担は?との質問には、「自動運転技術の開発自体はCruise社が担当しているが、日本における自動運転の開発にあたっては、Hondaの安全に対する考え方をしっかり共有した上で、日本の交通環境に適合させるための作業が必要、このためにも実証実験が非常に重要で、これはCruise社およびGM社と共同で進めていこうと考えている。自動運転を用いたモビリティサービスの領域は、GM社・Cruise社と協業して開発して行くが、一方、パーソナルカ―領域ではHonnda独自の開発を継続し、運転支援やその他技術の普及拡大は独自にやっていく、というように棲み分けを進めていく予定だ。」と述べている。気になるモビリティサービス事業の今後のロードマップについては、「2020年代半ばまでの国内での自動運転モビリティサービス事業の開始を目標に始めたが、まずは技術実証をしっかり進めていく。そのため本年度実験計画をスタートさせた。2022年には、自動運転車両の実験を公道でも開始できるように、今計画通り進めている状況だ。」と語る。担当の有吉氏は、今回の実証実験の目的について「Cruiseがサンフランシスコで培っている自動運転の技術を日本の関連法令や交通環境に適合し、安全の検証を行うことを主な目的としている。この実験では、まず地図作成車両を使い、自動運転車向けの高精度地図を作成する。その地図を使い、自動運転車両を走行させ、日本での実車検証を行う。自動運転車両の公道走行は2022年を予定しているが、安全性を十分に確認した上で、推進していく方針だ。」としている。自動運転実証を推進する上での技術者としてのやりがいは?との質問に対しては、「このCruise社の協業だが、All Hondaで推進している規模の大きなプロジェクトだ。大変さや難しさもあるが、現地のエンジニアとディスカッションを通じ、お互い良いものを創り上げて行くことに共感し、機能実現に向けた楽しさもある。このプロジェクト発の新しい移動手段の提供、それによる都市の活性化、地方の交通課題の改善など、社会貢献に向けた取り組みが出来ること、それがやりがいになっている」と語っている。サイト上では、ごく僅かだが自動運転モビリティサービスに投入される「クルーズ・オリジン」がテストコース上を走行するシーンも公開されている。また、2022年2月より始まった栃木県宇都宮市・芳賀町の公道上において始まった高精度地図用データの収集作業については、地図作成用の車両が建設中のLRTの線路の道路を走行する収集シーンを閲覧することが出来る。このデータの収集は3月下旬まで行われた模様だ。国も完成車メーカーも既に「織り込み済み」と思われるが、インタビュー内容にある「日本適合化開発」は、「Cruiseがサンフランシスコで培っている自動運転の技術を日本の関連法令や交通環境に適合し、安全の検証を行う」の言葉通り、海外勢と連携した完成車メーカーは、車両を市場投入する以前に「ローカライズ」の必要が生じ、自律運転プログラム等を自社開発したメーカーにも、クルマを市場投入後には新法の施行・関連法令の改正ごとに、自社が開発した自律プログラム・車両・搭載機器、サービス等を対応させる「即応体制」が必要であることを示唆する。完成車メーカーと自動運転技術開発会社の勢力図を、自動運転技術開発会社の視点から見直すと、ウェイモ(グーグル系/FCA、仏ルノー、日産、三菱自動車が連携)、アルゴAI(フォード出資、VWが連携)、アップル、リビアン(Amazonが出資)、そしてクルーズ(GM子会社、ホンダが連携)、TRI(トヨタ、スズキ、マツダ、SUBARUが連携)、ウーバー(トヨタ、デンソーが出資)などの勢力図が見えてくる。勢力図はこれら全てのグループが日本で、商用運行に入る段階で「法と自動運転プログラム」が互いに緊密に連動し、利用者の安全を守る必要を示している。
高精度3次元地図データが自動車開発シミュレーションソフトに採用~首都高速都心環状線の道路環境を忠実に再現~ 他
5月18日 日産自動車は昨年11月に長期ビジョン「Nissan Ambition 2030」を発表している。電動化を戦略の中核に入れ、移動と社会の可能性を広げる車と技術を提供するとしている。発表は、①日産が今後5年間で約2兆円を投資し、電動化を加速していくこと、②2030年度までにEV15車種を含む23車種の新型電動車を導入、グローバルの電動車のモデルミックスを50%以上に拡大すること、③全固体電池を2028年度に市場投入することなどが報じられている。社長兼最高経営責任者である内田 誠氏は、「社会のニーズや期待に応えるために、企業が果たすべき役割と責任は、ますます大きなものになっています。こうした大きな変化に対応するため、『Nissan Ambition 2030』では電動化の時代に向け、先進技術でカーボンフットプリントを抑制し、新たなビジネスチャンスを追及して行きます。そして、お客さまや社会から真に必要とされる持続可能な企業へと日産を変革して行きます。」と述べている。日産は、この目標達成に向け、2026年度までにEVとe-POWER搭載車を合わせて20車種を市場に導入し、各主要市場における電動車の販売比率を以下のレベルまで向上させるとし、グローバルにおける各市場での電動車の販売比率を公開している。比率は、欧州(75%以上)、日本(55%以上)、中国(40%以上)、米国では2030年度までに40%以上(EVのみ)のようになっている。最高執行責任者であるアシュワニグプタ氏は、「日産は、長い技術革新の歴史とともに、EVシフトを推進してきました。今後も日産は、この新しいビジョンとともに、お客様がよりスムーズにEVへ移行して行けるよう、ドライビングの楽しさを提供し、EVがより受入れやすい環境を用意することで、よりクリーンな世界の実現を目指します」と語っている。この発表の中では、リチウムイオン電池の技術を進化させ、コバルトフリー技術を採用することで、2028年度までに1kWhあたりのコストを現在と比べ、65%に削減するとしている。また、2028年度までに自社開発の全固体電池(ASSB)を搭載したEVを市場投入することを目指し、2024年度までに同社の横浜工場内にパイロット生産ラインを導入するとしている。ASSBの採用により、様々なセグメントにEVを投入することが可能となり、動力性能や走行性能も向上させることが出来、また充電時間を1/3に短縮し、EVをより効率的で身近なものにして行きますとしている。ASSBのコストは、2028年度に1kWhあたり75ドル、その後EVとガソリン車のコストを同等レベルにするため、65ドルまで低減して行くことを目指すとしている。日経新聞に掲載された日産の副社長で技術開発を担当する中畔 邦雄(なかぐろ くにお)氏に、日経BP総合研究所客員研究員の鶴原 吉郎(つるはら よしろう)氏が行ったインタビュー記事には、前述の日産の発表について、日産の狙いはどこにあるのかに焦点が当てられている。鶴原氏は日産の発表した電動車のモデルミックスを2030年度までにグローバルで50%以上とする目標は日米欧の競合に比べ電動化に消極的に見えるとし、今回の計画の真意について質問している。これに対して中畔氏は、「技術の価値に納得していただいて、初めて(EVが)お客様に受け入れられるが、EVに対する社会受容度はグローバルの市場により異なる。欧州のEV化は比較的早く、日米はそう簡単ではない」と語っている。さらに「日産が30年に電動車比率50%というのは、最低予測数値。顧客が日産の提供するEVに価値を見出し、日産を選択するならそのような期待に応えられるよう準備を進める、大切なのは国や地域の顧客の選択肢を用意すること」だとした。鶴原氏は次に、EV量産化のパイオニアとなった日産だが、現在は完成車メーカーが電動化に積極的に取り組んでいる。日産の強みはどこにあるのかと質問している。これに対し中畔氏は、「モーターとバッテリーを持ってくれば誰でも優れたEVを作ることが出来るわけではない、顧客にとっていかに価値ある商品を作れるかが重要だが、一朝一夕では出来ない」。リチウムイオン電池には客家の危険性があることも指摘した上で、どのように品質の高いものを安定して製造し、積載したクルマの安全性をどのように確保するか、これら様々な課題にサプライヤーと協力しながら取組んできた経験と実績をアピールしている。続いて鶴原氏は、近く商品化が予定される「軽自動車EV」について、地方では軽自動車が重要な移動手段となるが、「SS過疎」(ガソリンスタンド不足)となる地域も増加しているが、このような状況下で日産が軽EVを出す意味を訪ねている。中畔氏は「軽自動車は日本の自動車販売の4割を占める事実とともに、SSは減少、給油するまで往復40分走行する必要がある地域を引き合いに出し、EVなら過程でも充電可能で「SS過疎」を解消でき、近く日産が発売する軽EVは加速の良さ、乗り心地、いずれも従来製品とは別次元、長距離でも疲労が少なく、価格も実質購入価格は200万円~の見込みだ。(軽EVは)すべてのお客様へEVを届ける、(という目標)を実現するゲームチェンジャーだ」と述べている。但しこのためには、「全固体電池」が商業化する必要がある。日産は、商業化にいち早く「メド」を付けている。中畔氏は、「メドをつけたとは言わないが、全固体電池の技術的な課題を克服する方針は立てられた、これにより実用化に向けた作戦と道筋が見えてきた」という。全固体電池は、リチウムイオン電池と比較して、使用時の上限温度が高いため、急速充電性の向上が期待される。日産が目指す全固体電池は従来と比較して、充電時間を約1/3に短縮し、使い勝手が向上する。さらに電池のエネルギー密度を2倍に高める目標を置いたとしている。これにより航続距離に対する電池のサイズをコンパクト化し、コスト改善につなぐとともに車両パッケージングの自由度も岳めることが出来る。これらを通してガソリン車と同等の使い勝手や価格を備えたEVを実現できると期待しているとした。二氏の話題は運転支援技術「プロパイロット」にも及んだ。鶴原氏の「運転支援技術の商業化においても、グローバルの競争は激化している。日産は今後どのように運転支援技術を発展させるのか?」との質問に対する中畔氏の回答は次のようだ。「同技術は顧客から高い評価を得ており(運転負荷を軽減し快適に移動できるとの評価)、ハンズオフ走行は実際に高い比率で利用されている」とした。その上で中畔氏は「プロパイロット」を進化させる上で、(クルマの)外部状況を認識するセンサーの重要性に言及し、25年度以降に向け開発中の「プロパイロット」では新たなセンサー技術「グラウンド・トゥルース・パーセプション」を採用するとしている。同センサー技術は、従来のカメラ、ミリ波レーダーに加え、次世代LiDARの搭載により遠方の障害物を発見する能力が飛躍的に高まるとしている。更にカメラ、レーダー、次世代LiDARのセンサーフュージョンにより、車両と道路構造の区別、周囲物体の動きの把握、新たに周囲にある立体構造物の3次元的な形状や位置を高い精度で計測することが出来るようになる。これにより道路上に急に障害物が発見された際にも、ブレーキだけでなくステアリングの操舵も組合せ、緊急回避を実現させることができる。高速よりさらに高度な一般道での運転支援も、幹線道路などから実現されるという(ご参考:https://youtu.be/x332lbm_fDI)。一方でこれら完成車メーカーの「ビジョン」について、その足元を再考する必要があるとする意見やニュースも見られる。Touson自動車戦略研究所、自動車・環境技術戦略アナリスト、工学博士の藤村 俊夫氏は、各国政府や自動車メーカーの戦略について意見を述べている。掻い摘むと、気候変動による世界の被害としてシベリアの永久凍土が溶け始めていることを例に挙げ、気候変動対策をしなければ、CO2やメタン、ウイルスの放出による新たなウイルス禍、海水へのCO2吸収量減、森林火災頻発など、気候破壊の連鎖反応が危惧される(「ここ10年で真剣にCO2を下げないと2030年以降の人類の未来はない、企業経営の話ではなく、生きるか死ぬかの問題だといっても過言ではない」)と警鐘を鳴らす。また同氏は、燃料のグリーン化なしにはCO2削減目標は達成できないと指摘している。日本における2018年の1次エネルギー(*1次エネルギー:化石燃料も再エネも原子力も含む)の構成比は、46%が電力、54%が電力以外(内訳は、88%が化石燃料、9%が風力、太陽光、地熱などの再エネ、原子力が3%)である。同時に示された2018年における日本の1次エネルギーの消費構成を見ると、46%を占める電力の内訳は、家庭と業務、産業の一部で、電機以外の残り54%は運輸と産業で消費している。現在、経産省がエネルギー基本計画(成長戦略)で対象にしているのは電力のみだという。その他の54%はどうするか?についての方策は示されておらず、不十分な計画だと意見を述べている。電力以外のエネルギーに対するグリーン化政策の必要を訴える。先日、市場投入された韓国の自動車メーカー現代(ヒョンデ)の「IONIQ 5」(アイオニック ファイブ)の存在も気になるところだ。美しい幾何学的なラインを身に纏ったハッチバックは、同社のBEV(バッテリーEV)の最新車種であり、FCEV(燃料電池車)となる「NEXO」(ネッソ)と同時デビューしている。「IONIQ 5」(ベースモデル)に搭載されたリチウムイオン電池は58kWh、その他モデルはすべて72.6kWhで、4WD仕様は前後にモーターを搭載、システム全体で最高出力225kW(305PS)/2800-8600rpm、最大トルク605Nm(61.7kgfm)/0-4000rpmを発生すると聞く。リチウムイオン電池は、何れもAC200Vの普通充電とCHAdeMO仕様の急速充電に対応する。CHAdeMOの急速充電(90kW)では、80%充電まで32分という。RRモデルの価格は479万円~549万円、4WDは589万円で今後80万円の補助金が受けられるという。日産アリア(ARIA B6)は、FWD車でバッテリー容量は66kWh、最高出力は160kW、最大トルクは300Nm、航続距離(WLTC)は「IONIQ 5」の498kmに対して470km、(EPA推計では「IONIQ 5」が約398km、アリアは約376km、急速充電最大出力は「IONIQ 5」が90kW、アリアが130kW)、最後にアリアの価格は539万円~となる。何よりも同車の実力を顕著に示すのは、その充電時間だ。日経新聞(「現代自、EV充電5分200キロ 急速・大容量化、テスラやアウディも 海外勢先行、日本は遅れ」 https://www.nikkei.com/article/DGKKZO60873070X10C22A5TB2000/)によれば、米テスラや韓国・現代は出力250kW超の急速充電に対応、「IONIQ 5」は5分間の充電で、200キロメートルの走行を可能にしているという。これに対し、現状のトヨタ車や日産車は出力が150kW以下、充電時間は2倍以上と言われる。現在の「日の丸BEV」が国際的なEV競争の波を乗り切るには、まだまだ前途多難な状況だ。世界における自動車産業のEV競争に勝機を見出していくには、産業の根幹をなすエネルギーや環境問題について、関係省庁の迅速で絶え間ない支援が必要と言えるのではないか。